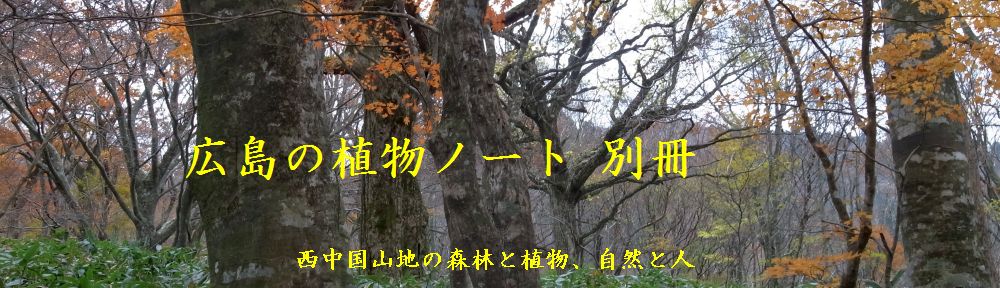スギ花粉の問題から、スギ林の存在自体を嫌悪される方は少なくない。私自身、関東に移住して約10年で発症(スギ花粉症が認識される以前)した。霞が関に勤務していた頃は、「花粉症の原因は林野庁」との抗議電話を受けていた。お怒りは良く分かります。
春先に、小笠原島に滞在すると、3日目には花粉症の症状がピタリと止むので、スギ花粉の影響が実感できる。もちろん、首都圏に戻れば翌日から元に戻るのが残念。
1.スギ天然林:西中国山地の天然スギ(アシウスギ、ウラスギ)はブナ林中の岩角地、過湿地に集団で生育している。広島県の「八郎杉、ハチロウスギ」、山口県の「寂地杉、ジャクチスギ」は同じもの。尾根の岩角地や凹地の湿潤地で自生の集団を作る。適潤地に植栽すると、ブナなどの広葉樹に押されてしまうが、下刈りなど、初期保育を行うことによって、最大の成長を示す。「土地的極相」の典型である。

2.天然生スギ林:いわゆる秋田スギの天然林は、伐採後に発生した稚樹を刈り出し、保育した。

3.高齢スギ人工林:人工スギ林であっても、80年生ともなると、林冠に隙間ができるので、亜高木層、低木層がよく発達する。

4.択伐されたスギ林:林業としての手入れがきちんと行われ、下層木が伐採されているので見通しが良い。草本層が良く発達しているのは、樹冠層に隙間がある証拠。


5.崩壊スギ林:「広葉樹林を伐採してスギ林にしたから崩壊した」と言われた崩壊地。

6.切り捨て間伐:間伐は行なったが、材価が搬出する費用に満たないので林内に放置されている。

スギ林にも色々あり、残念な事例も少なくないが、日本で最も重要な森林であることに葉違いない。これを活用できるかどうかは人次第。
スギの分布はこちらでみられる。
(初稿:2018年10月30日)