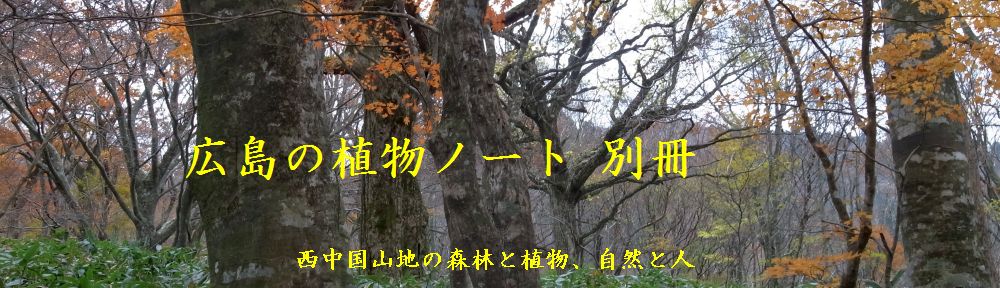栽培植物を追加する予定が滞っていた。
上蒲刈島のカワヅザクラが咲いているとの報道があった。気づけば、サクラの季節も近い。そこで、よく知られている園芸品種をいくつか追加した。広島では、五日市町にある造幣局広島支局の構内が最も多くの品種を揃えている。残念ながら、一般公開は年に一度だけなので、すべての花を見ることができない。ただ、年によって、開花期が2週間くらいずれるので、比較的早咲きが多くなったり、遅咲きが多くなったりする。毎年通っていれば8割くらいは見られるのではないか。
造幣局の桜は大阪の造幣局が始めたもので、本当に「通り抜け」であって、ゆっくり見ることができない。もっとも、私が訪れたのは、1972年の11月だけ、開花期ではなかった。当時、私が勤務していた農林省林業試験場浅川実験林に、国のサクラ保全対策の品種保存施設として「サクラ展示林」が造成されていた(現在は森林総合研究所多摩科学園の桜保存林)。業務の参考に、樹木研究室一同で見学に訪れ、お話を聞かせてもらった。
広島支局では、見学者の数に対して歩道が広いので、ゆっくり観察できる。通り抜けでなく、「花のまわりみち」と名付けられている。この場所は平地なので、サクラの生育には必ずしも適していない。しかし、土盛りをしたマウンド上に植栽されているため、水はけが良く、人の踏圧を受けることもない。しかも、非常に大切に手入れされている。公開日の案内も丁寧であり、申し分ない。